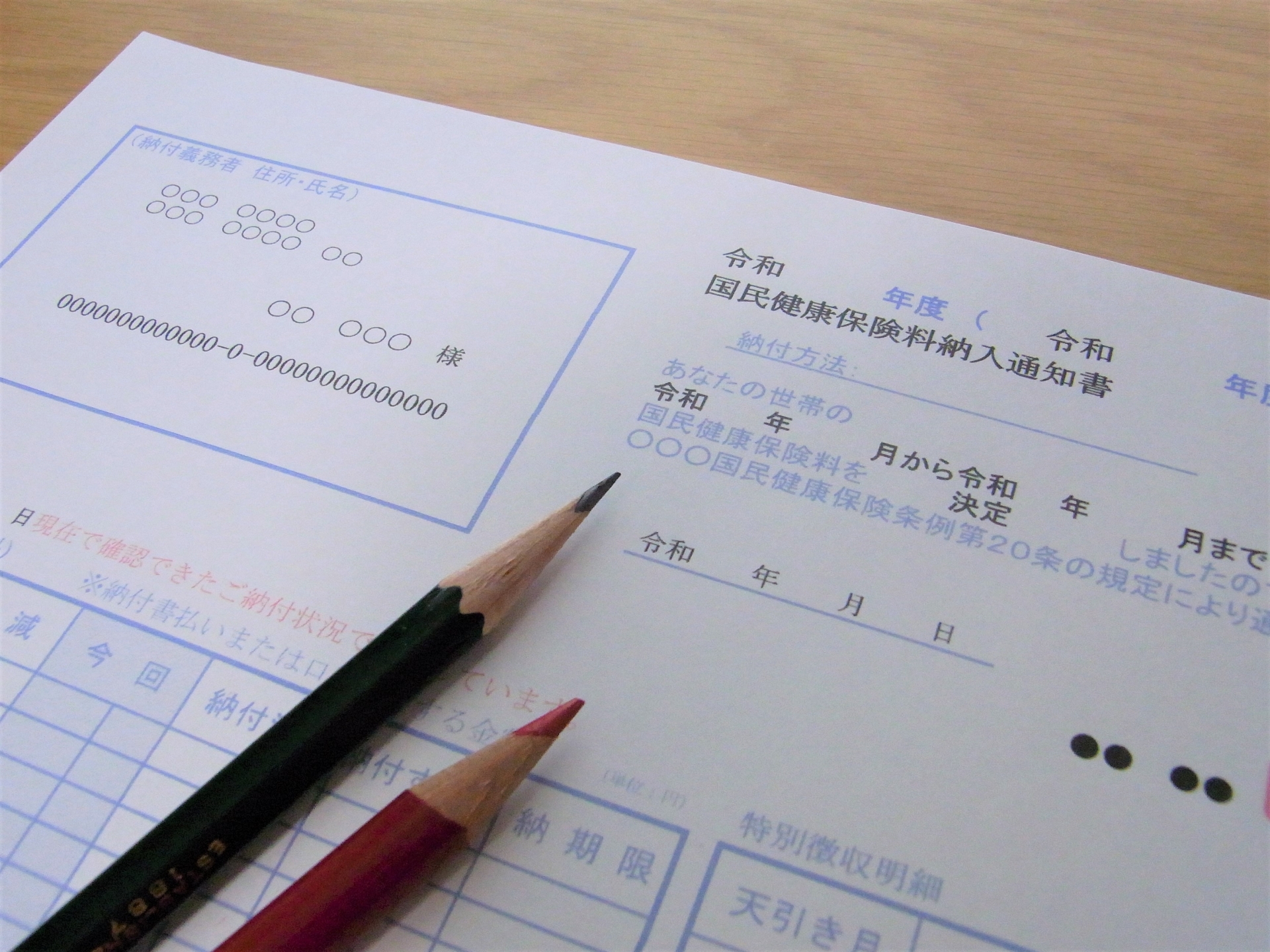
不動産の売却をすると健康保険料が上がる可能性があります。対象になる人は、国民健康保険・後期高齢者医療費制度の加入者・健康保険または共済保険の扶養家族です。
本記事では、不動産売却で健康保険料が上がる人や健康保険の種類、金額を抑える方法などを解説します。
なお、健康保険料の計算方法や保険料率は住んでいる地域によって異なりますので、該当する健康保険の各窓口にて確認をお願いします。
目次
不動産売却で健康保険料が上がる3つのケース

不動産を売却すれば誰でも健康保険料が上がるわけではありません。対象となるのは次のケースに当てはまる場合です。
<不動産売却で健康保険料が上がる3つのケース>
- 1.国民健康保険の被保険者
- 2.後期高齢者医療制度の加入者
- 3.健康保険・共済保険の被扶養者
3つのケースに当てはまる場合、不動産を売却すると年間の所得額が上がるため、健康保険料が上がる可能性があります。対象となる人の詳細は後ほど詳しく解説します。
健康保険の種類

まずは健康保険の種類から解説します。日本では国民皆保険制度が定められていて、健康保険に加入していると病気やケガをした時に、医療費の一部が負担してもらえます。
健康保険は無職の人であっても全員加入しなければなりません。健康保険の種類は主に4つの種類に分けられます。
1.会社員が加入する「健康保険」
健康保険は、民間企業の会社員と扶養家族が加入する健康保険です。正社員・嘱託社員・パート・アルバイト・契約社員が加入できます。
健保組合と協会けんぽに分かれていて、健保組合は主に大企業の会社員が多く、協会けんぽは中小企業の会社員が多いのが特徴です。健康保険料は、月給を基準とした「標準報酬月額」で決まります。
2.公務員・私立学校の教員が加入する「共済保険」
共済組合は、国家公務員や地方公務員・私立学校の教職員が加入する健康保険です。国家公務員共済組合・地方公務員共済組合・私立学校教職員共済制度など、それぞれの共済組合に分かれています。健康保険料は、月給を基準とした「標準報酬月額」で決まります。
3.自営業・無職・年金生活者などが加入する「国民健康保険」
国民健康保険は、自営業・個人事業主・非正規雇用者・年金生活者・その扶養家族が加入する健康保険です。退職などの理由で、企業の健康保険・共済保険の対象ではない人も国民健康保険に加入します。国民健康保険は、都道府県・市町村が連携し運営。
健康保険料は世帯の所得・加入人数によって異なり、1年間の所得を算定した後、それをもとに翌年の健康保険料が決まります。ちなみに、国民健康保険には被扶養者の概念がなく、加入者一人ひとりが健康保険料を負担します。
4.75歳以上が加入する「後期高齢者医療制度」
後期高齢者医療制度は、75歳以上の人や65歳から74歳までで一定の障害があると認定を受けた人が加入する健康保険のこと。運営主体は後期高齢者医療広域連合です。
健康保険・共済保険・国民健康保険に関係なく、75歳以上になると自動的に後期高齢者医療制度に加入することになります。
後期高齢者医療制度では、世帯主ではなく被保険者一人ひとりが健康保険料を支払うと定められていて、金額は被保険者の前年の1年間の所得によって決まります。
不動産売却で健康保険料が上がる可能性がある人

健康保険の中で、不動産売却をして健康保険料が上がる可能性がある人は、国民健康保険や後期高齢者医療制度の加入者、健康保険・共済保険の被扶養者です。ここでは、健康保険料が上がる対象者を見ていきましょう。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者
国民健康保険と後期高齢者医療制度に加入している人は、不動産を売却すると健康保険料が上がる可能性があります。どちらも1年間の所得を基準にして、翌年の健康保険料を決定するからです。
自営業や無職の人などの場合、給与のように保険料の算定基準となるものがないため、世帯ごとの所得が健康保険料の算定基準となります。そのため一時的な所得であっても、不動産売却による譲渡所得(利益)は収入として算定されてしまうのです。
国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者は、不動産売却で得た譲渡所得によって加入者の年間所得が増えるため、健康保険料が上がる可能性があります。
健康保険・共済保険の被扶養者
健康保険・共済保険の加入者本人(被保険者)は、不動産を売却しても健康保険料は上がりませんが、扶養家族が所有している不動産を売却した場合は、健康保険料が上がる可能性があります。
扶養家族が不動産を売却して譲渡所得を得ると、一時的に高額所得者と認定され、扶養から外れ、国民健康保険に加入する場合があるからです。
扶養家族の要件は「年収が130万円以下、収入が被保険者の半分」であること。扶養から外れて国民健康保険に加入すると、所得によって健康保険料が決まるため、不動産を売却することで金額が上がる可能性があります。
ただし、扶養から外れるかは健康保険組合の方針によっても異なります。健康保険組合によっては一時的な収入で判断せず、継続的な収入で判断する場合も。加入する健康保険組合で要件が異なるので、不動産の売却を考えている場合はあらかじめ確認しておくと安心です。
不動産売却をしても健康保険料が上がらない人

不動産を売却して譲渡所得が発生しても、健康保険・共済保険の被保険者の場合は健康保険料が上がりません。
どちらも毎月の給料を基準にした「標準報酬月額」に、健康保険料率を乗じて健康保険料を算出するからです。そのため、不動産売却で譲渡所得を得ても給与としては計算されず、被保険者の健康保険料は上がりません。
しかし、前述したとおり、家族が所有している不動産を売却する場合は、負担が発生する可能性があります。
不動産売却で健康保険料が上がるのは譲渡所得が発生した時

不動産の売却で健康保険料が上がるのは、譲渡所得(利益)が発生した場合です。譲渡所得とは、売却金額から取得費と譲渡費用を差し引きした金額のこと。
譲渡所得が発生しなかった場合は、年間の所得が変わらないので、健康保険料が上がることはありません。譲渡所得の計算方法は次のとおりです。
<譲渡所得の計算方法>
譲渡所得=不動産の売却金額-取得費(不動産を購入した時の金額+仲介手数料)-譲渡費用(不動産の売却にかかった費用)
不動産を売却すると必ず健康保険料が上がるのではなく、譲渡所得が発生した場合に金額が上がります。
不動産売却で健康保険料の金額はどのくらい上がる?

健康保険料がどれぐらい上がるのかを算出するには、不動産を売却して得た譲渡所得を含めた金額と含めない金額を計算すると良いでしょう。
差額を計算することで、健康保険料がどのくらい上がるのかをイメージしやすくなります。まずは国民健康保険・後期医療制度の仕組みから解説します。
国民健康保険・後期医療制度の健康保険料算定の仕組み
国民健康保険は医療保険分・後期高齢者支援分・介護保険料分の3つで構成されていて、それぞれ4つに区分されています。
<4つの区分>
- ・所得割:所得から計算される金額
- ・均等割:世帯の保険加入人数から計算されるによる定額
- ・平等割:自治体ごとで決まっている金額
- ・資産割:固定資産より計算される(自治体によっては加算がない)
区分の中で不動産売却に影響されるのは所得割です。また、以下のように採用される方式によっても健康保険料が変わります。
<方式>
- ・4方式:所得割・均等割・平等割・資産割で計算される国民健康保険料
- ・3方式:所得割・均等割・平等割で計算される国民健康保険料
- ・2方式:所得割・均等割で計算される国民健康保険料
後期高齢者医療制度の健康保険料は、国民健康保険で解説した所得割と均等割の合計で計算されます。
保険料率は市区町村によって異なるので、お住まいの地域の窓口または公式Webサイトで確認してください。
計算方法
健康保険料は次の方法で計算します。
<計算式>
健康保険料=(世帯の総所得額-基礎控除額)×保険料率(各市町村で異なる)
令和3年の改正で基礎控除額は33万円から43万円に引き上げられました。基礎控除額は前年の合計所得金額に応じて異なります。
| 合計所得金額 | 基礎控除額 |
|---|---|
| 合計所得額が2,400万円以下 | 43万円 |
| 2,400万円超2,450万円以下 | 29万円 |
| 2,450万円超2,500万円以下 | 15万円 |
| 2,500万円超 | 適用なし |
世帯の総所得額に、不動産を売却して得た譲渡所得を含めた金額と、含めなかった金額の計算をして差額を出すと、健康保険料がどれくらい上がったのかがわかります。
具体例
不動産売却あり・なしの健康保険料の具体例を紹介します。
【条件】
- ・国民健康保険に加入していて、世帯所得額が500万円・配偶者が1人いる場合
- ・譲渡所得は100万円
- ・保険料率は、都道府県標準保険料率(令和6年度)で計算
【都道府県標準保険料率(令和6年度)】
| 医療保険の構成要素 | 所得割(%) | 均等割(円) |
|---|---|---|
| 医療分 | 8.91 | 53,722 |
| 後期支援金分 | 2.98 | 17,505 |
| 介護納付金分 | 2.42 | 17,589 |
【不動産売却ありの場合の具体例】
不動産売却ありの場合の健康保険料の合計金額は974,699円です。
<内訳>
・医療分 603,731円
所得割 (世帯所得500万円+譲渡所得100万円-基礎控除額43万円)×保険料率8.91%=496,287円
均等割 加入者数2人×53,722円=107,444円
・後期支援分 200,996円
所得割 (世帯所得500万円+譲渡所得100万円-基礎控除額43万円)×保険料率2.98%=165,986円
均等割 加入者数2人×17,505円=35,010円
・介護分 169,972円
所得割 (世帯所得500万円+譲渡所得100万円-基礎控除額43万円)×保険料率2.42%=134,794円
均等割 加入者数2人×17,589円=35,178円
【不動産売却なしの場合の具体例】
不動産売却なしの場合の健康保険料の合計金額は831,599円です。
<内訳>
・医療分 514,631円
所得割 (世帯所得500万円-基礎控除額43万円)×保険料率8.91%=407,187円
均等割 加入者数2人×53,722円=107,444円
・後期支援分 171,196円
所得割 (世帯所得500万円-基礎控除額43万円)×保険料率2.98%=136,186円
均等割 加入者数2人×17,505円=35,010円
・介護分 145,772円
所得割 (世帯所得500万円-基礎控除額43万円)×保険料率2.42%=110,594円
均等割 加入者数2人×17,589円=35,178円
不動産売却ありとなしで金額を差し引きすると、不動産売却ありの方が、143,100円高くなることがわかります。このように、年間の所得で健康保険料が変わる場合は、事前に計算して健康保険料がどのくらい上がるのかを把握しておくと、健康保険料の上昇対策をとることが可能です。
不動産売却で健康保険料が上がらないよう抑える方法

不動産の売却で譲渡所得が出たとしても抑えられる費用は抑えておきたいもの。ここでは不動産売却で保険料が上がらないよう抑える方法を解説します。売却前にあらかじめ費用を抑える対策としても有効な方法も紹介。
マイホーム売却なら3,000万円特別控除を活用する
売却する不動産がマイホームであれば、3,000万円特別控除を活用すると健康保険料の金額を抑えられます。3,000万円特別控除を活用し、譲渡所得から3,000万円を引いた金額が0円以下であれば健康保険料の金額は上がりません。
例えば、4,000万円で購入した不動産を5,000万円で売却した場合は1,000万円の譲渡所得が発生します。この時に3,000万円特別控除を活用すれば3,000万円を超えないため、翌年の健康保険料が上がりません。
<特別控除が適用される条件>
- ・売却する不動産が自分の居住用である
- ・売主と買主が親子・夫婦関係ではないこと
- ・併用不可の特例を受けていないこと
- ・売却した年の前年および前々年にマイホームの買換え・マイホームの交換の特例の適用を受けていないこと
など
もしも低所得世帯に対する軽減措置を受けている場合は、特別控除が受けられないため注意が必要です。マイホーム以外の特別控除は次のとおり。
| マイホーム以外の特別控除 | 内容 |
|---|---|
| 親のマイホームを相続して売却 | 譲渡所得から3,000万円を控除できる |
| 相続した土地・建物を一定期間内に売却 | 相続税を取得費に計上できる |
| 公共事業のために土地を売却 | 5,000万円を控除できる |
| 国土交通省が推進する特定土地区画整理事業などのために土地を売却 | 譲渡所得から2,000万円を控除できる |
不動産を購入した時の金額を把握する
健康保険料の上昇を抑えるには、年間所得を増やさないために不動産を購入した時の費用と、売却した時の費用の差を把握するのが大切です。不動産の購入時には、さまざまな費用がかかります。
<不動産の購入時にかかる費用>
- ・土地や建物の購入費用
- ・不動産会社の仲介手数料
- ・登記費用
- ・引越し費用
など
不動産を購入した時期が古く、かかった費用の証明書などがない場合は、売却金額の5%を概算取得費にできます。ただし、実際にかかった費用よりも概算取得費の方が低い場合は譲渡所得の金額が増える可能性があります。その場合は健康保険料が上がることも考慮しておきましょう。
不動産の売却にかかる経費を事前に計算して把握する
不動産を売却して発生する譲渡所得を把握し、売却時の金額を抑えると健康保険料が上がるのを抑えられます。不動産を売却する時には次の費用が発生します。
<不動産売却にかかる費用>
- ・不動産会社の仲介手数料
- ・司法書士への報酬
- ・売買契約書に貼付する印紙代
- ・引越し費用
- ・登記費用
- ・必要書類の取得費用
など
不動産を売却する時は、領収書などの売却にかかった費用を後で確認できるように保管しておきましょう。
不動産売却と保険料の注意点

不動産を売却すると介護保険料が高くなったり、確定申告が必要になったりする可能性があります。
介護保険料が上がる可能性もある
介護保険料も国民健康保険と同じく、所得によって金額が変わるため不動産を売却した場合、金額が上がる可能性があります。介護保険は40歳以上が加入する保険で、年齢によって第1号被保険者(65歳以上)と第2号被保険者(40歳以上65歳未満)と分かれています。
- ・第1号被保険者は、介護保険のサービス費用などから算出された額(基準額)をもとに、所得に応じて保険料を決定
- ・第2号被保険者は、加入している健康保険の算定方法で決定、医療保険料と同時に徴収
介護保険料の算定方法は加入している医療保険によって異なるので、保険料の相談はお住まいの市区町村で相談してみてください。
確定申告をする
不動産を売却して譲渡所得が発生した場合、特別控除を受けるには確定申告が必要です。また譲渡所得が出ると健康保険料だけではなく税金にも関係してきます。
確定申告は、不動産を譲渡した日の属する年の翌年の2月16日から3月15日までに行います。ただし、不動産の売却で譲渡所得が出なかった場合、申告は必要ありません。
不動産売却と住民税について詳しく知りたい方は以下の記事も参考にしてください。
不動産売却で健康保険料が上がる場合は対策を

不動産売却で健康保険料が上がる可能性があるのは、国民健康保険・後期高齢者医療制度の加入者、健康保険・共済保険の被扶養者です。
売却によって譲渡所得が発生しそうであれば、事前に不動産を購入した時の金額と売却する時の金額を把握して、健康保険料の上昇対策をしておきましょう。
不動産所有や不動産売却についてのご不安などお聞かせください!
1973年法政大学法学部法律学科卒業後、1977年に司法試験合格。1980年に最高裁判所司法研修所を終了後、弁護士登録をする。不動産取引法等の契約法や、交通事故等の損害賠償法を中心に活動。「契約書式実務全書」を始めとする、著書も多数出版。現在は「ステップ バイ ステップ」のポリシーのもと、依頼案件を誠実に対応し、依頼者の利益を守っている。





